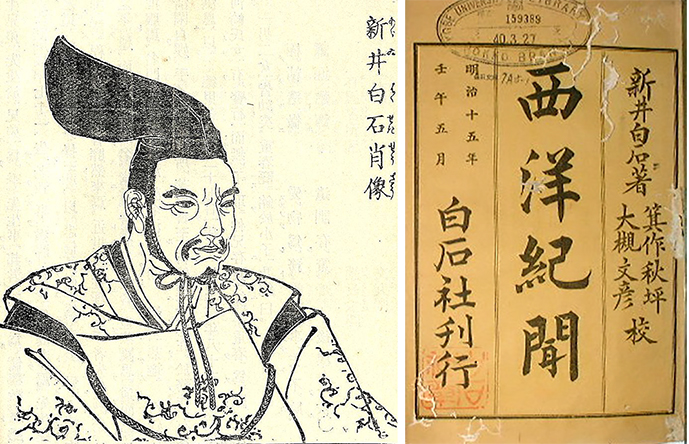
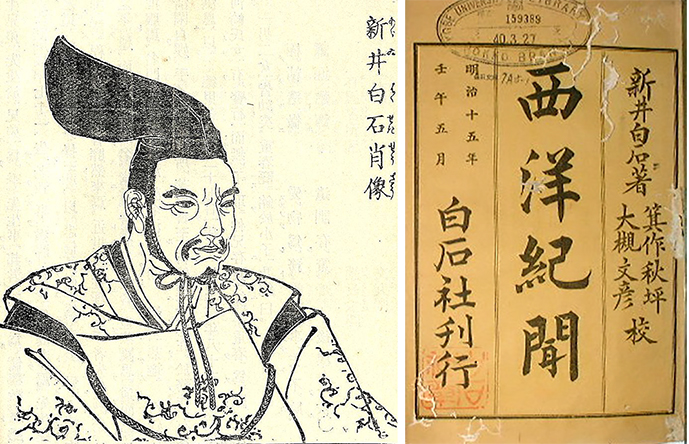
●外来語をすべてカタカナ表記に統一した儒学者・新井白石とその著録
さて、この複合表記の名人は誰かみなさんはご存知でしょうか。漢字に長けていながらも英国留学したことで、英語をまずはルビに置き換え、その単語の元の意味が何かを考慮して工夫しながら当て字を表現した人です。正解は夏目漱石で、「虞美人草」のなかだけでもかなりの外国語の漢字表記が見受けられます。
手巾(ハンケチ)、洋杖(ステッキ)、洋袴(ズボン)、洋琴(ピアノ)、洋卓(テーブル)、洋筆(ペン)、洋灯(ランプ)、肉刺(フォーク)、留針(ピン)、卵糖(カステラ)、小羊(ラム)、行為(アクション)、印気(インキ)、鉄軌(レール)、稜錐塔(ピラミッド)、論理的(ロジカル)などが挙げられます。
我が国には7世紀に「中国語=漢字」の音をあて、万葉仮名で対応、一六世紀頃、ポルトガル語が入ってきたときは上記の対応をしました。六代将軍・家宣、七代将軍・家継に側用人として仕えた儒学者・新井白石[明暦3年2月10日(1657年3月24日)〜享保10年5月19日(1725年6月29日)]が現われると、1709年から1716年までの約7年間、後に「正徳の治」と呼ばれる文治政治改革を行いました。そして自身の著録『西洋紀聞』のなかで、外来語を全てカタカナ表記に統一することで異文化のニュアンスを上手く伝えることに成功しました。明治時代までは単位など外来語にまだ漢字をあてていましたが、使い勝手や視認などの問題があり、徐々に外国語・外来語には「便利なカタカナ」を使うようになり、昭和27年(1952)には公文書で外国語・外来語を使う場合はカタカナを使用することという通達が出たのです。
よくぞ日本語には漢字の他にカタカナとひらがながあったものだ、「夜露死苦」と胸を撫でおろす筆者です。